井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2024.10.03
9月30日、県議会の会派・民主フォーラムと、私たち無所属県民会議が共同で埼玉県警察本部に「安心して安全に生活できるための緊急要望」を提出しました。

この緊急提出の背景には、川口市内の2つの痛ましい事件があります。
===
9月23日、乗用車と原付きバイクが衝突し、バイクに乗った少年2人が死傷したひき逃げ事件で、市内のトルコ国籍の18歳の男性が自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致死)と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕された。事故に遭った男性2人はいずれも市内に住む日本人の17歳の建設作業員と16歳の高校生で、建設作業員は死亡、高校生は意識不明の重体である。
<事件②>
9月29日、飲酒運転の車が乗用車と衝突する事故があり1人が死亡した。中国籍で無職の18歳の容疑者は逆走運転をしており、酒気帯び運転と過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕され、容疑を危険運転致死に切り替え捜査をしている。
==
日本で生活する以上、「郷に入っては郷に従え」は当たり前であり、交通ルールをはじめ、守るべきルールがあります。
しかし、一部外国人住民による目に余る行為が多発し、安心した暮らしを阻害する行為が横行している現状もあります。
川口市のことも特出ししつつ、対応をお願したのは、全県下のことであり、全ての国籍に関わる話です。
要望書提出の場でもコメントしましたが、川口市での事件・事故が報じられるために、県内での他市でも同様の不安が広がります。
そのたびに県警の対応への注目も集まります。既にやっていただいているところも十分承知ですが、事件・事故を減少させ、県民が安心して安全に生活できるよう、以下の6点について早急な対策を要望しました。
1 警察官の増員をし、人的基盤の強化
2 川口市内のパトロール強化
3 川口市内の資材置き場周辺での暴走運転の取り締まり強化
4 飲酒運転撲滅に向けての取り締まり強化
5 無免許運転撲滅に向けての対策強化
6 国と連携し不法滞在者の取り締まり強化
要望の様子は、翌日の埼玉新聞にも掲載されました。
この先も、安心して安全に生活できるための取組を進めていきたいと思います。
2024.10.02
昨日10月1日は、私の誕生日でした。
本当に多くの方からSNSなどを通して
お祝いのメッセージをいただきました。
お祝いのメッセージをいただきました。
さて、「45歳」になりました。
40歳になった時も感慨深いものがありましたが、45歳という年齢も節目のひとつと感じています。
昨年の改選から、会派の代表を務めるようになり、これまで以上に仕事や公務の幅が広がりました。
(※写真は、会派代表者として「議会災害連絡本部会議のオンライン会議」に参加している様子です。7人の会派なので、会派代表の私は、いわゆる“お誕生日席”に座っています。)
子育ても、子どもが大きくなるに連れて楽になるのか、と思っていましたが・・・そんなことないですね
小さい時よりも自分自身の「やりたいこと」「やりたくないこと」がハッキリしてきて、それに「しっかり応えていこう」「やりたくないことでも取り組めるように支えよう」と思うと、親の出番はむしろ増えていくのだなぁ、と痛感しています。
日々、仕事か、家事か、子育てかと日々慌ただしい時間を過ごしています。
それ故に、成し得ていないこともありますが、少しでもあらゆることに前向きに臨んでいきたいと思います。
45歳という節目の年になり、ひとつ感じているのは「積み重ねてきた経験は、着実に身に付き、活かせるようになっている」ということです。
選挙で選ばれて議員として活動している私にとって、その“経験”を与えてくれているのは、市民の皆さまであり、県民の皆様です。
だからこそ、その経験を通して得たモノを、これまで以上に、市民・県民の皆様にお返し出来ればと思っております。
至らぬことも多々ございますが、引き続きのご指導をよろしくお願い致します。
2024.09.26
昨日の出来事とのことですが、共学化議論のキッカケとなった市民団体の要望書を、日吉 享教育長が直に要望書を受け取ったといいます。
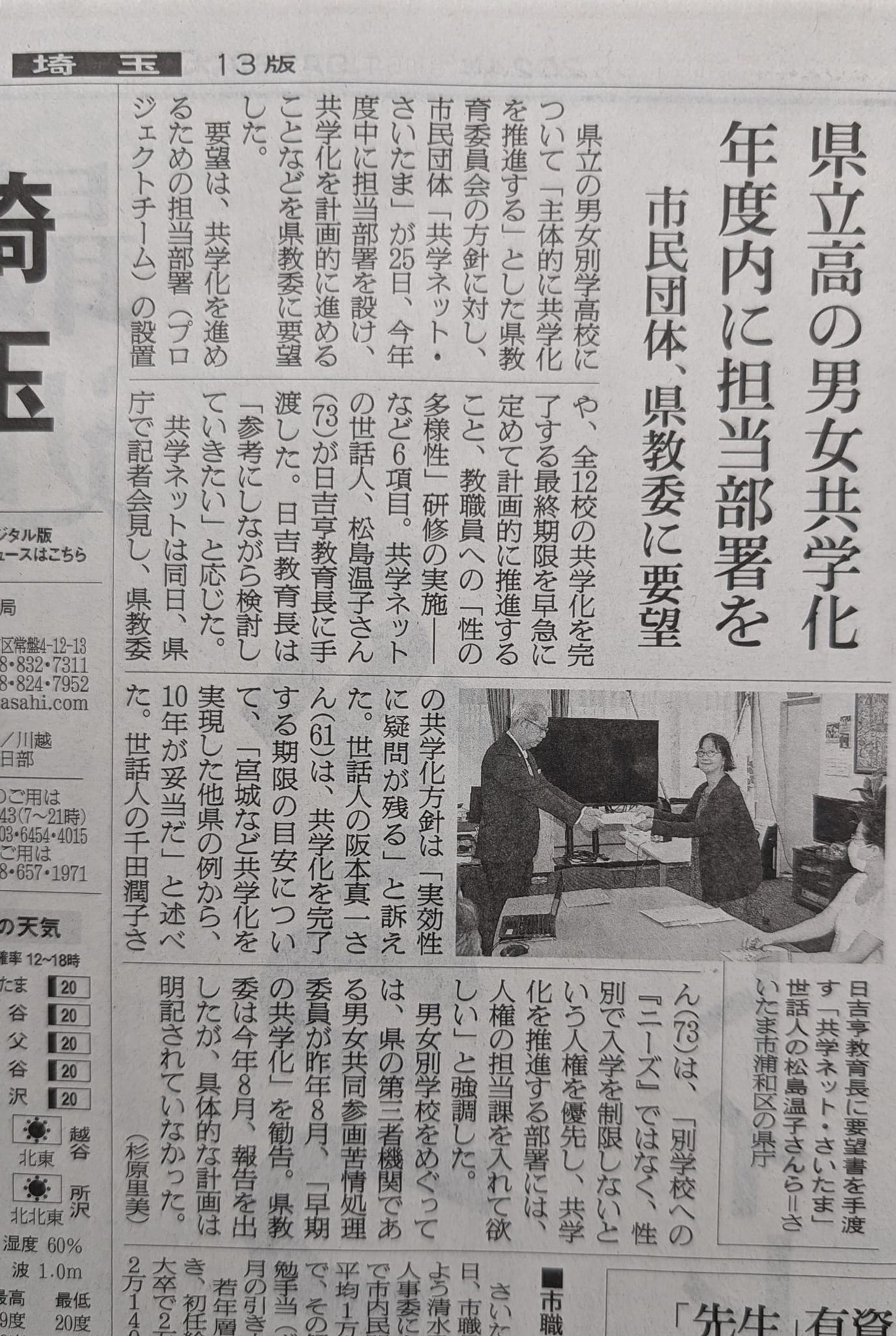
県教委の「勧告への回答」が出る前に行なわれた、別学校の生徒たちの代表者が集まった際の別学維持を求める要望書は、代理とも言える高校改革統括監だったのに。。。
ちなみに、そもそも #共学化反対 なので、期限を設けるのも私は断固反対です。
なお、記事内に市民団体のコメントが載っています。
「別学校への『ニーズ』よりも、性別で入学を制限しないという人権を優先すべき」
という“比較論”ではなく、
「別学校への『ニーズ』ではなく、性別で入学を制限しないという人権を優先すべき」
という別学へのニーズを“否定”して語っています。
別学を選ぶ子供たちの中には、やむを得ない事情で共学を避けたい子供も居ます。
そういう子供のニーズ(声)を“否定”して掛かるこの団体の主張に、これ以上教育局が振り回されること、そして何より、子どもたちの教育環境が振り回されることがないよう、切に願いたいです。
2024.09.26
「しばcafe」は、柴崎光子市長と和光について語るイベントです。
↓ しばさき市長のツイッターより。

今朝は一緒に駅立ちを行いました。

↓ しばさき市長のツイッターより。
今朝は一緒に駅立ちを行いました。
来月開催予定の第1回目は女性の方が参加しやすいように、“女性限定”で開催します。
場所:オーチャードカフェ
(練馬区大泉学園町8-22-17)
参加費: 500円(ワンドリンク付)
対象:和光市在住の女性(小さなお子様連れ可)
私は当日ファシリテーター(進行役)で参加します。
詳しくはチラシまたは下記より。
2024.09.01
和光市内の台風10号の影響は大きく出なかったようですが、全国では多大な爪痕が残されました。心からお見舞いを申し上げます。
さて、まだまだ暑い日も続いていますが、それでも夏の終わりを感じます。
さて、まだまだ暑い日も続いていますが、それでも夏の終わりを感じます。
この夏は、市内各地のラジオ体操に柴崎市長と共に伺いました。
その際には時局の話もしたり、県政に纏わるお話もします。
直近では、北原小学校で開催されたラジオ体操にお邪魔しました。(写真1)
その際、県道である、北原小学校横のアンダーパスのある道路の「歩道の草刈り」のご相談をいただきました。写真2の赤色部分です。
朝霞県土事務所と相談の上、先週、実施の方向で動いてくれています。
歩道を中心に行い、車道についても危険な箇所は対応する予定です。
昨週の段階で、台風10号が到来が見込まれていたため、予定の変更や実施順序の変更も想定されますが、児童や地域の安全のため、早めに対応したいと回答をいただいています。有難いです。
実は、夏が終わるこれくらいの時期は、河川を含め雑草刈払いの繁忙期なのです。
(場所によっては、元々予定が組まれている場合もありますし、タイミングが合わず見送られるケースもあります。)
もし、和光市内で他にもお気づきの箇所などあれば、ご相談いただければと思います。
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事